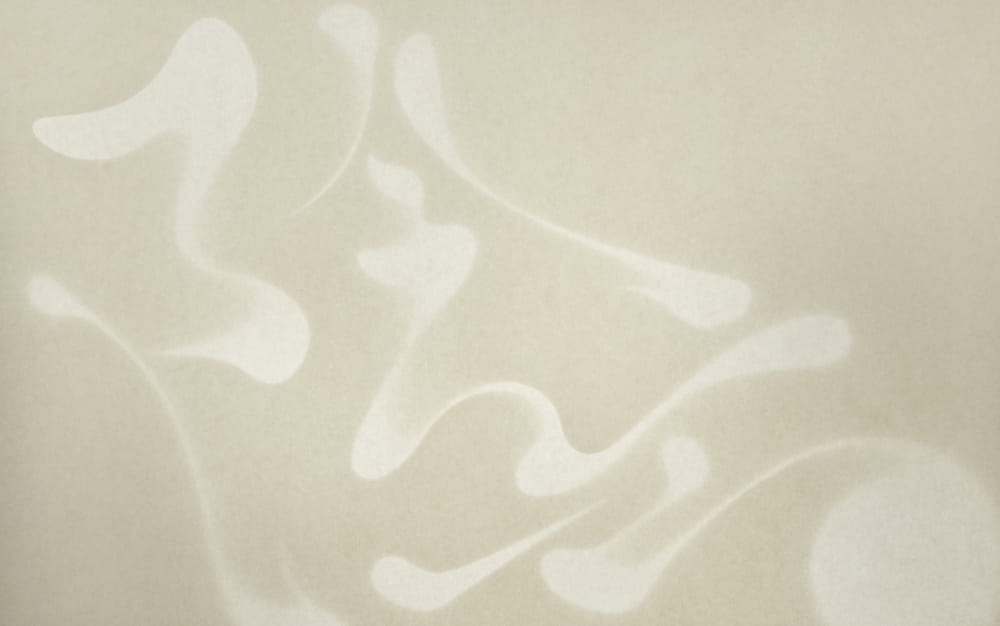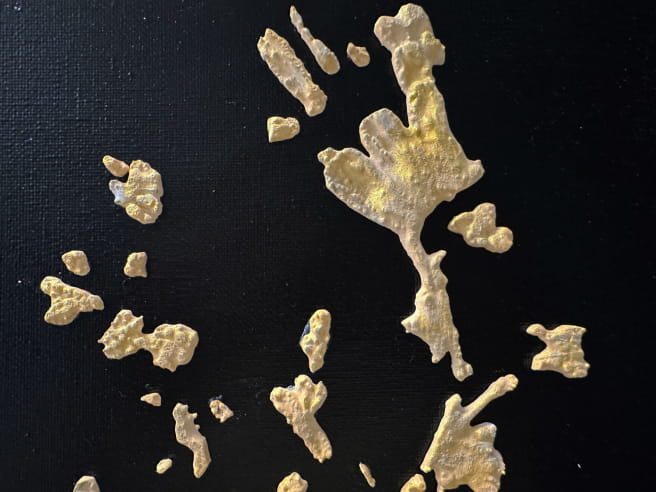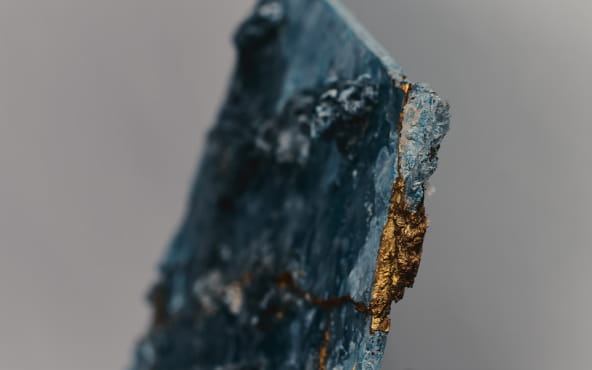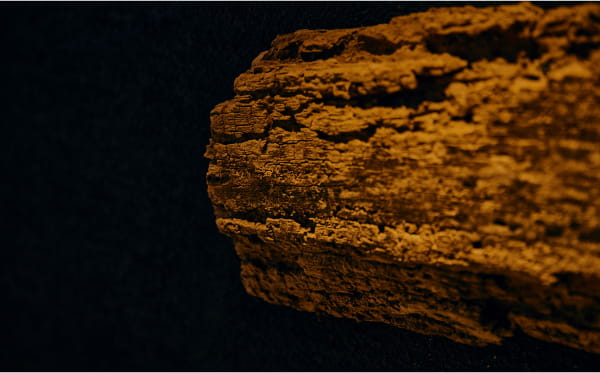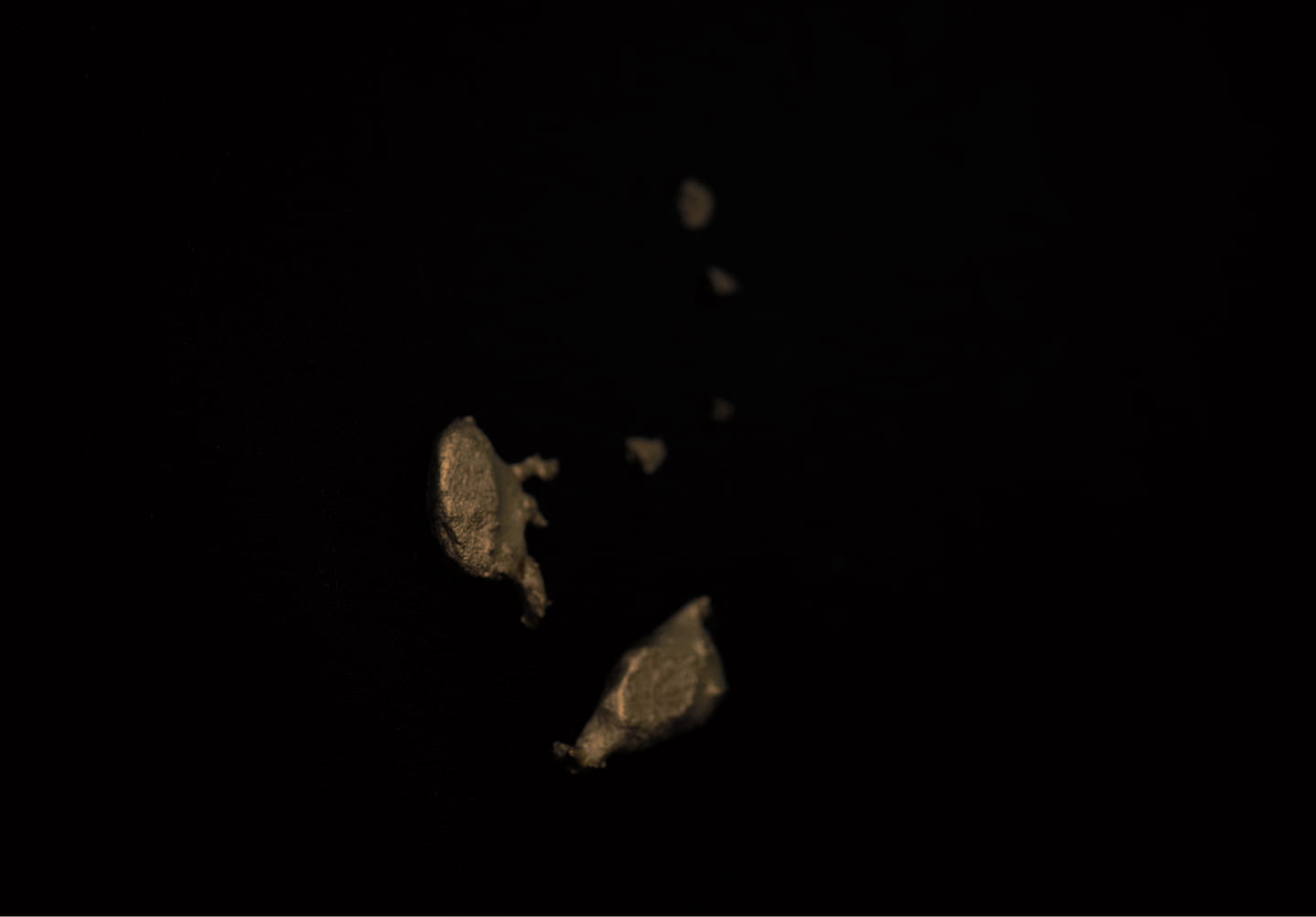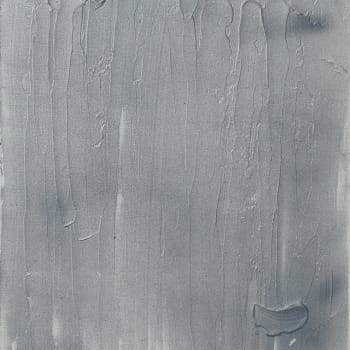2025.02.20
こんにちは。山崎晴太郎です。
余白のアートフェア福島広野が終わりました
まだ各種精算業務は残っていますが、「余白のアートフェア 福島広野」が広野町の二ツ沼総合公園「合宿の宿」「清明館」「パークギャラリー」を会場として無事に開催出来たことを深くお礼申し上げます。

会場をお貸しいただいた株式会社広野町振興公社さま、後援をいただいた広野町さま、株式会社広野町振興公社さま、広野町商工会さま、広野町観光協会さま、福島県さま、在日ウクライナ大使館さま、そして協賛いただいた三愛化成商事株式会社さま、リープ株式会社さま、株式会社トークアイ 代表 佐野良太さま、株式会社
折茂製作所さま、株式会社アドバイザービルマンさま、ハタゴイン福島広野さま。
皆様のご協力でなんとか形にすることができました。
本当にありがとうございました。
また、この事業は経済産業省の「映像芸術文化を通じた関係人口創出事業 ハマコネ(HAMA
CONNECTED)」の助成金をいただいて実施したものですが、
実施に際してアドバイスをいただきましたハマコネ事務局の皆様、Yamaide Art Office株式会社の皆様にもお礼を申し上げます。

さて、かしこまったご挨拶はここまでにして、ここからはいつものように。
僕がこの「余白のアートフェア福島広野」でやろうとしたのは、これからのアートイベントのあり方の一つとしてのパイロットプログラムでした。
パイロットのもともとの意味は、港や海峡など、危険な水域を安全に通過させるために船に乗り込んで案内をしてくれる、水先人です。
それが転じて、テレビ番組などで実際に視聴者がどんな反応をするかを試してみるための試験的な番組もパイロットと呼びます。パイロット番組の反応が良ければ本格的に番組を作るわけです。
改めて振り返る今だからこそ言えることですが、「余白のアートフェア福島広野」にはいくつものハンデキャップがあったと思います。

まず、運営委員会の代表企業を務めた僕たち、セイタロウデザインにはアートフェアを開催した経験が無いこと。
これまで福島県の浜通りでは「見るもの」としての現代アートは沢山ありましたが、「買うもの」としての現代アートは恐らく、これが初めてになるということ。
展示会場や美術館のような、この手のイベントのための施設ではなく、合宿所や茶室や公民館のロビーのような空間での展示になること。
東京から、というよりも日本のどこからも想像以上に遠いこと。
これらいくつものハンデを乗り越えて、アートフェアが「成功」した、アートフェアをやって良かった、と地元の皆さん、アーティストの方々、そして僕たち自身もそう思えるような形とは何かを考えながら奮闘した三ヶ月でした。

その中で僕が一番大事にしていたのは、出展していただくアーティストの皆さんの熱量をどれだけ最大化できるかということです。
現代アートというとクールなものという印象をお持ちの方も日本には多そうですが、実際には現代アーティストの皆さんは、本当に熱い思いを原動力にして活動をしています。現代アーティストたちの生の熱が集積する場もあって良いはずだというのが、僕の考えです。

僕の経験から言うと、こうした公募型の展示即売会では応募したときに提出した作品以外の展示は基本的に認められません。
公募の審査のときにキュレーターが展覧会のテーマに合ったものだけを採用しているのだから、当然ですといえば当然です。
ですが、「余白のアートフェア福島広野」では、もうこれ以上は保険契約が間に合わないというギリギリまで、出展作品決定のデッドラインを遅らせました。
そうすることで、今まさにそのアーティストが熱量を持って取り組んでいる創造行為を、熱を保ったまま会場に集めることが出来るのではないかと思ったからです。

また、作品の展示方法も全て運営で決めてしまうのではなく、アーティストの方々が話し合い、力を合わせ、助け合って展示空間を創るというやり方にしました。
これも、結果として、そこに集まったアーティストさんたちの創意工夫や作品への思い、そして同じ空間を共有する隣人たちへの配慮が詰まった空間が幾つも連なる、奇跡のようなイベントになりました。

今、現代アートを美術館に見に行くと、真っ白な壁の部屋に作品が飾られています。あの空間はホワイトキューブと呼ばれるもので、今から100年ほど前にボストン美術館で始まり、1930年頃にMOMAが完成させた展示方法です。作品をそれ以外のものから完全に切り離して、作品だけを純粋に味わおうという考え方です。
一方、もっと昔にできたルーブル美術館やプラド美術館は王様の宮殿の内装を残したまま作品を展示しています。
今回、ホワイトキューブ式の展示を広野町でやることも現実的に言って不可能でした。それならばいっそのこと、集まったアーティストたちの息遣い、熱気、願いや祈りのようなものでそれぞれの部屋を満たしてもらった方が良いのではないか。そんな考えから挑戦した展示方法でした。現代アート風に言えば、ある種の「社会的彫刻」のニュアンスもあったのかもしれません。

そしてもう一つ、飼い犬を連れて広野町まで来られた石川琢弥さんと、あるほなつきさん以外の全てのアーティストとスタッフがハタゴイン福島広野に泊まったこと。
これもアーティストたちの熱を高めるのに効果的だったと思います。
実はハタゴインの立ち上げのデザインはセイタロウデザインが担当しており、コンセプトやデザインのルールは以前に我々が作ったものでした。1階の共用部は、西洋のインや日本の旅籠のように、旅の途中で出会った人たちがそこで語り合い、縁を結んで次の目的地へと出発していくような空間に。そんな思いを込めて提案した名前が「ハタゴイン」でした。その狙いは今回、見事に実を結んだと感じます。僕自身、レセプションの夜は会ったばかりのOchiroさんと盛り上がり過ぎて、翌日は見事に二日酔いになってしまいました。

こうして幕を閉じた余白のアートフェア福島広野。公募で審査員をお願いした県立ふたば未来学園美術部の皆さんからは、また来年もありますよねとキラキラした目で尋ねられてしまいましたし、参加されたアーティストさんの中には早くも来年はどんな展示にしようかと考えておられる方もいらっしゃるようです。閉幕後に心のこもったメッセージを送ってこられたアーティストさんも何人もいらっしゃいました。
その思いに、出来る限り応えていければと考えています。
今のところ、なんとか(助成金のおかげで)収支はトントンをくらいですみそうな雲行きです。「余白のアートフェア 福島広野」を今後ともよろしくお願いいたします。
新着情報
3月にソウル近郊のCzong Institute for Contemporary Artで開催されるグループ展に参加します。Czong Institute for Contemporary Artは韓国人の現代アーティスト、キム・チョンホさんが設立した現代アートセンターで、“Art Is 2025 - Part 2”という展覧会です。会期は3/12-30です。
この他、着々とその他の展示も決まっています。また公式発表が出ましたらお知らせしますね。
近況情報をお伝えするニュースレターを配信しています。
購読ご希望の方は、下記フォームにお名前とメールアドレスをご記入ください。